もののようすをあらわすことば(形容詞)をたくさん知って実際に使えるようにしていくことは、表現力を高めるためには重要です。
お子さんが言葉を話し始めの頃は、もののなまえ(名詞)の語彙を増やすことを意識されてきたと思いますが・・・
次の段階として言語や文章の表現力を高めるためには、”うごきことば”(動詞)や”ようすことば”(形容詞)の語彙を増やしていくことが必要になります。
今回は、教室の年少さん~年中さんクラスで「ようすことば」を表現力につなげていくステップとして行っている取組をご紹介します。
『ようすことば』を身につける取組3つ
①『ようすことば』のカルタとり
『ようすことば』のカルタとりで使用するものは、さまざまなもの(食べ物、生き物、乗り物等々・・・)が描かれた絵カード。
使う絵カードはどんなものでもOKですが、教室で使用している『わらべきみかのあいうえおカード プラス』のように、描かれているものの種類にある程度バリエーションがあったほうが良いと思います。

幻冬舎(Gentosha) わらべきみかのあいうえおカード プラス
遊び方は、
出題者が『ようすことば』を言って、その言葉に合うものを、ばらばらに並べた絵カードの中から見つけて取ります。
例えば、赤い→りんご、まるい→ボール など。
ようすことばの意味を理解し、実際のものと結びつけることで表現力につなげるのがねらいです。
なお、1つの『ようすことば』に対して、答えは1つでなくてもOK。
例えば、ほそながい→バナナ、電車、へび等・・・その言葉にあてはまっていれば正解です。
取るほうに慣れてきたら、子どもにも出題してもらいましょう。
②『ようすことば』をたくさん言おう
『ようすことばをたくさん言おう』で使用するのは、①と同じ絵カード。
絵カードを見て、そのもののようすをあらわす言葉をたくさん言っていきます。
たとえば
「ウサギ」なら→「しろい」「かわいい」「やわらかい」「はやい」
「電車」なら→「ながい」「はやい」「かっこいい」「うるさい」
などなど・・・
1つのものを色々な角度(形・色・触感・味、種類、機能など)から見るトレーニングことで、1つのものから発想をどんどん広げていく拡散的思考をやしないます。
やり方は、子どもに順番にカードを見せて、できるだけたくさん言わせるという方法でも良いですが、親子でゲーム形式にするとさらに盛り上がります。
または交代で言っていき、言えなくなったら負け!
たくさんカードをゲットできた人が勝ち!
・・・などなど、いろいろと工夫してみてくださいね。
③ようすことばの連想ゲーム
『ようすことばの連想ゲーム』では、ようすことば(形容詞)が書かれたカードを見て、そのことばに当てはまるものを出来るだけたくさん答えさせます。
①のようすことばのカルタとりと同様、ようすことばの意味を理解して、実際のものと結びつけることで表現力につなげるのがねらいです。
遊び方は・・・
めくったカードに書かれた”ようすことば”から思いつくモノを順番に言っていき、たくさん言えたほうが勝ち、となります。
子どもに一方的に言わせるだけでなく、ゲーム形式にして勝負することで俄然盛り上がります!
必要なものは、1枚に1つ「ようすことば」を書いたカード。
市販のものでもよいですが、バリエーションがたくさんあるほうがよいので、白紙カードにどんどん書いて、手作りしましょう。
”ようすことば”といってもたくさんあるので、何を書けばよいのか迷ってしまいますが・・・
いわゆる「反対ことばカード」には、子どもにもわかりやすく、かつ使用頻度が高いことばが選ばれているため、そういったものを参考にしても良いですね。![]()
ちなみに、くもんの『反対ことばカード』には、以下のような”ようすことば”が記載されています。
・ながい⇔みじかい
・ふとい⇔ほそい
・おおい⇔すくない
・おもい⇔かるい
・あつい⇔うすい
・あたらしい⇔ふるい
・かたい⇔やわらかい
・つよい⇔よわい
・はやい⇔おそい
・たかい⇔ひくい
・ひろい⇔せまい
・とおい⇔ちかい
・ふかい⇔あさい
・あつい⇔さむい
・あかるい⇔くらい
これらに「まるい」「しかくい」などの”かたち”をあらわす言葉や、「あかい」「きいろい」などの”色”をあらわす言葉を加えてもいいですね。
教室では、上記のような”反対ことば”に加えて「たのしい」「むずかしい」「かわいい」「いたい」「まぶしい」「こわい」「かしこい」など、たくさんの形容詞を使って行っています。
※なお、くもんの『反対ことばカード』には、上記以外に
・たつ⇔すわる・ねる⇔おきる・はく⇔ぬぐ・あける⇔しめる・はいる⇔でる・いく⇔かえる・まげる⇔のばす・のる⇔おりる・あがる⇔さがる・うごく⇔とまる
・・・といった、”うごきことば”(動作をあらわすことば)の反対語も掲載されています。
『擬音語』でもやってみよう
形容詞とおなじく様子を表す言葉として『擬音語』があります。
『擬音語』とは、音や声、ものの様子などを言葉であらわしたもの。
レッスンでは上記の取組を、形容詞ではなく『擬音語』しばりでも行っています。
擬音語を細かく分類すると、
(ワンワン、二ャーニャー、わいわい、ぺちゃくちゃ等)・自然の音や物音をあらわす「擬音語」
(ドンドン、バタバタ、ザーザー、ジャブジャブ等)・音ではなく動きや様子をあらわす「擬態語」
(キラキラ、つるつる、さらさら、ふわふわ等)
などに分けられます。
子どもに『擬音語』の意味を説明するのはむずかしいのですが、意味を理解させなくてもOK。
いくつかの例をあげていくうちに何となくわかってくれる感じです。
知っていそうで意外と子どもの『擬音語』の語彙は少ないもの。
例えば『カエルの鳴き声は?』と聞くと、子どもの場合「ケロケロ」などという定形化された表現ではなく、聞いた音をものすごくリアルに声帯模写(!)してくれたりして、一般的な『カエルの鳴き声』の表現を言えなかったりします。
やはり、日常会話や絵本などをとおして『擬音語』の表現に触れる機会をたくさんつくってあげることが大事ですね。
『ようすことば』の獲得には実体験が大事!
ご紹介した取組では、あるものの様子をあらわす言葉をたくさん言うことを通して、今までに獲得した「ようすことば」が実際にどんな場合に使うかを理解し、実際に使えるようにすることを目指しています。
また、ひとつのものを色々な角度(形・色・触感・味、種類、機能など)から見ることで、1つのものから発想をどんどん広げていく拡散的思考(思考の柔軟性)をやしなう、という目的もあります。
例えば、ウサギの絵を見て「しろい」や「かわいい」など、目で見てわかる色や形状などをあらわす言葉は、出てきやすいと思います。
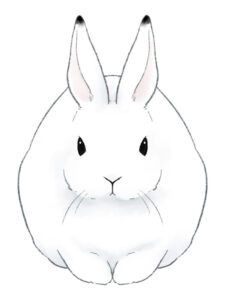 一方で、ウサギの耳はイヌやネコとくらべて「ながい」とか、触ってみたらとっても「やわらかい」など・・・
一方で、ウサギの耳はイヌやネコとくらべて「ながい」とか、触ってみたらとっても「やわらかい」など・・・
そのものを単純に「見る」だけでなく、じっくり観察して他のものと「比べる」、また実際に触ったり、体験して「感じる」といったことをしないと、出てこない表現があります。
絵を見て『擬音語』を言う取組をしていた時、ある年中さんの男の子が「絵本」の描かれたカードを見て、「えほんを読むと、心がポカポカします。」と言ったのを聞いて、ものすごく感動したことがあります。
何かしら心を動かされる実体験をともなってこそ!
スポンサーリンク
最後に
ようすをあらわすことばを使って表現をするには、ことばを知識として知っているだけではなく、見て・触って・体験して感じたことと、ことばを意識して結びつけてあげる必要があります。
まずはベースとなる生活体験を豊かにすること、そして普段から日常会話の中で、気持ちや様子をあらわすことばの表現になるべくたくさん触れさせてあげるよう意識することも大切ですね。
*こちらの記事もよく読まれています▼▼▼
「マジカルバナナ」~連想ゲームで『拡散的思考力』をやしなおう
スポンサーリンク




