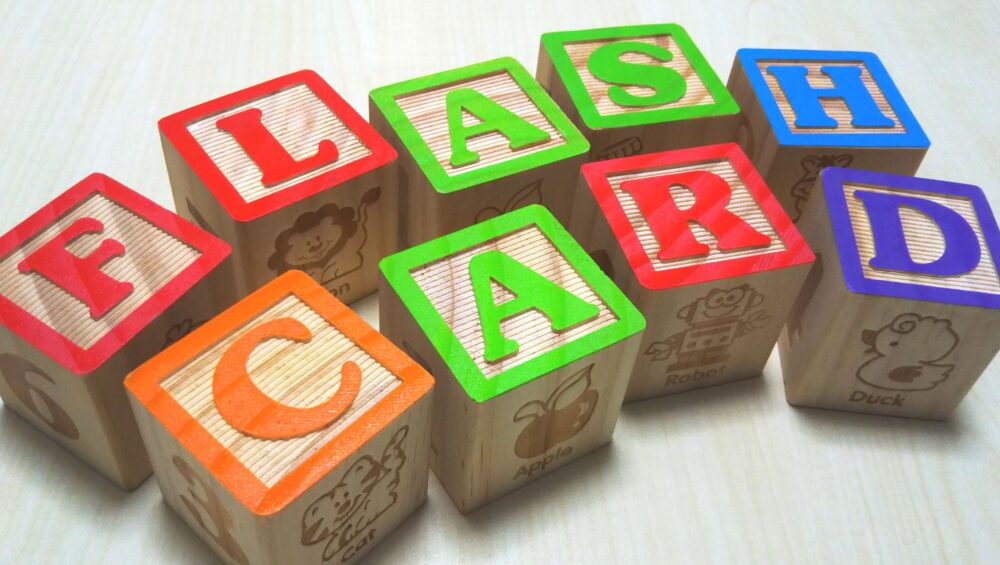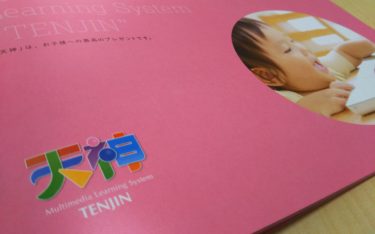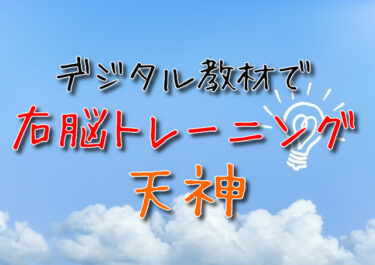七田式などの幼児教室で使われているフラッシュカード。
おうちでの知育にフラッシュカードを取り入れられているご家庭も多いと思いますが、正しいやり方で見せなければ、せっかくの効果が得られなくなってしまいます。
そもそもフラッシュカードの目的とは?
フラッシュカードの目的は、「右脳の力を引き出すこと」にあります。
言語を介して理解する論理・理屈の「左脳」に対し、イメージを介するひらめき・直感の「右脳」というように、右脳と左脳では、脳の働きがちがいます。
右脳は、左脳がついていけないほど高速で大量の情報に反応して動き出します。
カードの内容を知識としてインプットさせるのはもちろんですが、フラッシュカードのいちばんの目的は、知識の習得ではなく右脳を活性化することなんです。
カードフラッシュをする時の注意点
1枚1秒以下のスピードでフラッシュする
ここがいちばん大事なところです。
左脳が追い付かないほど高速の刺激でないと右脳が働きません。
七田の教室にはじめて体験レッスンなどで来られたお母さまが、ものすごい勢いでめくられるフラッシュカードを見てぎょっとされている姿をよく見ましたが・・・
初めて見る方がちょっとひいてしまうくらいの速さが求められます。
最初はなかなか難しいと思いますが、練習あるのみです。
すばやくカードフラッシュするための必須アイテムが「指サック」です。
私の講師時代は、いかにも「事務員さん」が伝票をめくるときに使っていそうな、指全体をおおうタイプのものを使っていました。
こんな感じのです↓
今は指先だけにはめるタイプの、見た目も可愛い商品がありますので便利ですね!
指で絵や文字が隠れないように気をつける
カードフラッシュをする時は、カードを持つ指でカードの絵や文字が隠れてしまわないよう気をつけましょう。
例えばドッツカードの場合、カードを持つ指でドッツの一部が隠れていたら、読み上げられる数字と見ているドッツの数が合わないままインプットされてしまいます。
だいたいのフラッシュカードはその点を見込んで、持ちやすいようカードのふちの余白が大きく取られています。
白紙カードを買ってフラッシュカードを手作りする場合は、この点に注意して、あまりカードの端から端までキチキチに絵や文字を入れないようにしましょう。

☆七田式(しちだ)フラッシュカード教材☆ 白紙カード(小)☆★
また自分ではそのつもりがなくても、カードを持つ指が文字や絵にかかってしまっていることもあります。
自分ではなかなか気付きづらいですが、鏡の前でフラッシュしてみると、子どもからカードがどのように見えているのかが確認できます。
取り組み全体をテンポよく行う
とにかく、右脳の取り組みは始めから終わりまで素早くテンポよく、が鉄則です!
スポンサーリンク
フラッシュカードの効果的なやり方:4つのステップ
上でお伝えした注意点を踏まえた上での“効果的なフラッシュカードのやり方”とは、「年齢に合わせて適切なやり方で見せる」ことです。
3歳くらいまでの右脳が優位に働いている時期は、カードを見せてインプット(見せる・聞かせる)をメインに行います。
左脳が働き出す時期(3歳以降)インプット+アウトプット(言わせる)で、インプットした内容がさらに定着します。
お子さんの年齢や発達段階によってカードフラッシュの方法を変えることによって、さらに効果が上がります。

【七田式教材:しちだ右脳教育】【対象年齢 0歳~5歳】かな絵ちゃん日本語ABセット
なお『かな絵ちゃんカード』は、表側に絵・写真、裏側に文字(そのものの名前)が書かれています。

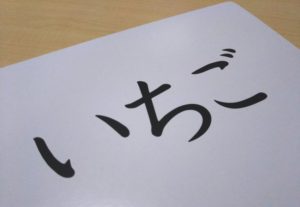
※フラッシュカードには、『かな絵ちゃんカード』のように両面のものと、片面のみ(裏面に、表面の絵に関する説明などが書かれている場合も含めて)のものがあります。
フラッシュカード(かな絵ちゃん)の見せ方STEP①(0~2歳くらい)
表側の絵のみ(片面)を見せてフラッシュ。
絵を見せながら、絵の名前を読み上げます(インプット)。
フラッシュしたあと、フラッシュしたカードのうち2枚を見せて、「りんごはどっち?」「犬はどっち?」などと問いかけ選ばせる(手で正しい方を指し示させる)「どっち遊び」もやってみましょう。
まだ言葉が出ない0歳〜のお子さんでもできるアウトプットの取り組みです。
フラッシュカード(かな絵ちゃん)の見せ方STEP②(2~3歳くらい)
絵・写真と文字の両側を見せてフラッシュ(絵・写真→文字)しながら文字を読み上げます(インプット)。
表面を見せたら、そのカードをすばやくひっくりかえして裏側も見せます。
フラッシュのスピードが遅くなったりテンポ感が狂わないように気をつけましょう!
文字の読み上げは、
・絵を見せている時と文字を見せている時の両方(2回)言う
・文字を見せている時のみ言う
の2パターンがあります。
フラッシュカード(かな絵ちゃん)の見せ方STEP③(3~4歳くらい)
カードを見ながら言葉を復唱させます(アウトプット)。
カードをフラッシュしながら、フラッシュする人が言葉を読み上げ、それを子どもが復唱します。
かな絵ちゃんカードであれば、両面フラッシュで表面を見せている時にフラッシュする人が言葉を言い、裏面を見せた時に子どもが復唱して言います。
見ているカードの絵・文字と、口で言う言葉のタイミングが合っていることが大事になります。
フラッシュカード(かな絵ちゃん)の見せ方STEP④(4歳くらい~)
フラッシュしたカードを見ながら、子どもに自分で言葉を言わせます(アウトプット)。
絵を見ながら言うことでことば(語彙)が育ち、文字を見ながら言うことで文字の読みの力が育ちます。
スポンサーリンク
フラッシュカードを選ぶ際の注意点
フラッシュカードを選ぶ際には、どんなジャンルの内容を見せるかはもちろん大事ですが、「フラッシュしやすいカードかどうか」も重要です。
「フラッシュのしやすさ」は、カードのサイズや紙質などによって変わってきます。
大きすぎたり小さすぎたりするものはフラッシュには向きません。
カードの大きさや紙質がフラッシュに向いていないと、フラッシュのスピードが遅くなったり、途中でカードを落としてしまったりしやすくなります。
そうなると、右脳に働きかけることはできませんし、子どもの集中力も切れてしまいます。
七田から出ているフラッシュカードはフラッシュが前提なので、すべてがフラッシュに適した、フラッシュしやすいサイズ・紙質です。
※ちなみに、『かな絵ちゃんカード』を含め七田のほとんどのフラッシュカードのサイズはA5版(A4の半分のサイズ。148㎜×210㎜)となっています。

【七田式教材:しちだ右脳教育】【対象年齢 0歳~5歳】かな絵ちゃん日本語ABセット
おうちでの知育によく用いられる『くもん』の各種カードは、いろんなジャンルが揃っていて、その中から必要なジャンルだけを選べるのでとても便利ですよね!?
(その点『かな絵ちゃんカード』は最小単位が600枚で、その中にさまざまなジャンルのカードが入っているのですが、特定のジャンルだけ見せたい場合には不向き。)
しかしながら『くもん』のカードはフラッシュを目的として作られていないため、とってもフラッシュしにくいのです。

くだものやさいカード(1集)第2版 (くもんの生活図鑑カード)
『くもん』のカードの多くは表面に絵、裏面にそのものの説明が書かれているタイプ。
子どもにゆっくり絵を見せながら、それがどんなものかを教えてあげる、というような、「知識のインプット」や「さまざまなものへの興味・関心をそだてる」といった、絵本や図鑑的な使い方が向いていると思います。

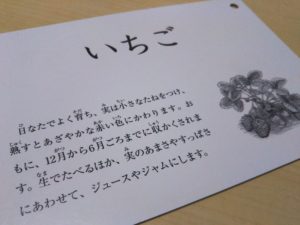
スポンサーリンク
子どもがフラッシュカードを見てくれない!原因と対策
親御さんが一生懸命カードをフラッシュしているのに「子どもがぜんぜん見てくれない・・・」という場合があります。
そんな時の、考えられる原因とその対策についてお伝えします。
お子さんが右脳モードになっていない
そのためには、取り組みをする場所の周りを片付けて、気が散るようなものを置かないようにしましょう。
また、時間がない中バタバタとあわただしく行うのではなく、できるだけ余裕がある時間帯に落ち着いて取り組むようにしましょう。
七田式などで知られる「右脳トレーニング」と言えば、フラッシュカードや、暗唱などの記憶トレーニングが頭に浮かぶ方が多いと思いますが・・・ 七田の教室では、それらの右脳トレーニングには「プリレッスン」というものがセットになっています。 […]
カードフラッシュのスピードが遅い
上でお伝えしたとおり、右脳は高速で大量の刺激に反応します。
左脳が追い付かないほど高速の刺激でないと右脳のスイッチが入りません。
もしお子さんがカードを集中して見てくれない場合、カードフラッシュのスピードが遅すぎる可能性があります。
1枚1秒以下のスピードでフラッシュできるよう、ひたすら練習しましょう。
またフラッシュのスピードがはやくても、カードの入れ替えにもたついたりしていないか等、取り組み全体を通してテンポよく行えているか、再度見直してみましょう。
カードに飽きてしまった
白紙カードを使って、お子さんが今興味のあるものを題材にしたフラッシュカードを手作りするのも良いですね。
アウトプットを求めている
その場合は、上の『フラッシュカードの見せ方』の項目を参考に、「選ばせる」「言わせる」などのアウトプットを取り入れてみてください。
親御さんの気分が安定していない
親御さんのそのような気分はお子さんにも伝わって、ますますリラックスした状態にならず悪循環に陥ってしまいます。
親子ともども落ち着いた気分のときに取り組むようにしましょう。
以上、お子さんがカードフラッシュを見てくれない、という場合に考えられる原因とその対策についてご紹介しましたが・・・
いろいろと工夫をしてみてもどうしても効果がない、という場合には、思い切ってフラッシュカードの取り組みはお休みして、少し間を開けてから再度取り組んでみましょう。
おうちでの右脳トレーニングに欠かせないのがフラッシュカード。 七田(しちだ)のフラッシュカードの定番が「かな絵ちゃん」です。 おうちで「かな絵ちゃん」に取り組んでいる方は多いと思いますが、単にフラッシュして見せているだけ、という方も[…]
フラッシュカードがどうしてもうまくできない場合には。
ここまでカードフラッシュのやり方や注意点などについて述べてきましたが・・・
「自分にはできる自信がない」
「やってみたけど、うまくいかなかった・・・」
「カードフラッシュの練習をする時間なんてない」
という方も多いと思います。
その場合、”パソコンやタブレット上でフラッシュカードを見せられる教材を使う”という手段があります。
フラッシュカードや記憶などの右脳トレーニングができる学習教材『天神』をこちらの記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
タオ社の『天神』幼児版は、フラッシュカードが2,352枚、かず・すうじカードが1,196枚入っているなど、右脳トレーニングを学習に取り入れたいと考えているご家庭におすすめな教材。 デジタル教材ならではの特性で、手軽に右脳トレーニングが[…]
タオ社の家庭学習教材『天神』は、パソコンやタブレット上で学習するデジタル教材ですが、学習内容や購入の仕組みなど、他の通信教育とは一線を画す、ちょっと珍しい教材。 中でも『天神』幼児版は「おうちで右脳教育ができるレアなデジタル学習教材」[…]
最後に
フラッシュカードは右脳を活性化し、さまざまな知識をインプットすることができる知育教材ですが、ちょっとしたことで効果が半減したり、逆により良い効果が得られたりもします。
これからフラッシュカードに取り組もうとされている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
おうちで右脳トレーニングができるデジタル教材『天神』の関連記事はこちら>>>右脳トレーニングができるオススメのデジタル教材『天神』関連記事一覧
ここでは、右脳トレーニングができるオススメのデジタル教材、タオ社の『天神』に関する記事をまとめてご紹介しています。 *天神タブレット版の体験でわかったメリット・デメリット。天神でフラッシュカードする時の注意点と、効果の出る使い方をお伝[…]
※おうちでの右脳トレーニングの取り組み方を以下の記事にまとめています。よろしければご参考になさってくださいね!
七田(しちだ)式などの幼児教室で実践されている右脳教育。 左脳にはない優れた力があると言われる右脳の力を伸ばすことを目的としています。 「右脳教育に興味はあるけど、教室に通うのは金銭的にも時間的にもちょっと難しい・・・」 「教室の[…]