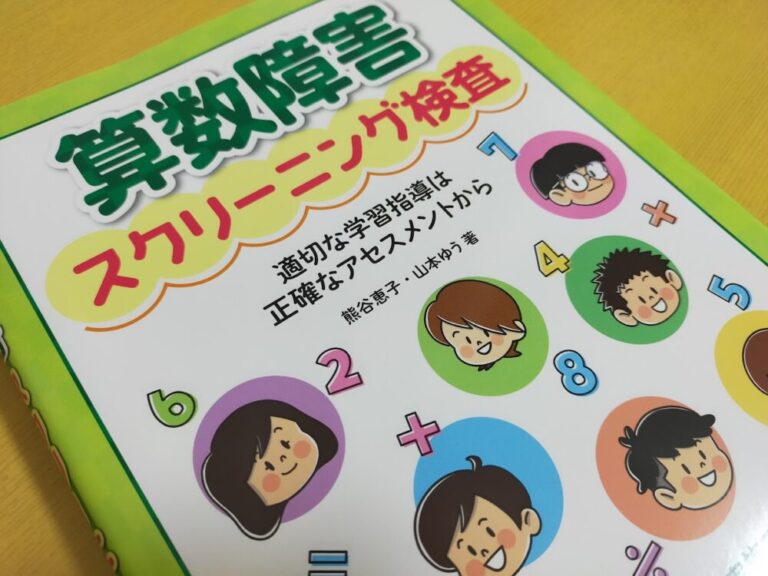『算数障害スクリーニング検査』は、就学前の幼児さん・小学生の「算数の苦手さ」を数値化し、算数障害の可能性を明らかにするだけでなく、「苦手さの背景」をつかんで、できるだけ早く適切な方法で指導や支援が行われることを目的とした書籍。
就学前と就学後の学年ごとに、スクリーニングテストの検査用紙と記録用紙が付いていて、コピーしてそのまま使用できるようになっています。
基本的には教育や支援の現場での使用を目的としたものですが、ご家庭で実施することも可能。
何より、就学前までにどのような算数の力がついていればよいのかの目安がわかるため、幼児さんや小学生のお子さんを持つ親御さんの参考になる書籍です。
今回の記事では、
・『算数障害スクリーニング検査』の就学前検査で測られる力
・就学前までにどのような算数の力がついていればよいのかの目安
・就学前に、必要な算数の力をつけるために意識すること
・・・についてご紹介します。

算数障害スクリーニング検査: 適切な学習指導は正確なアセスメントから (学研のヒューマンケアブックス)
算数障害とは
算数障害は、学習障害の領域「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」の中で、「計算する」「推論する」に困難があること。
以下の4つの領域に整理できます。
算数障害の4つの領域
①数処理・・・数詞・数字・具体物の対応関係
➁数概念・・・序数性と基数性
③計算・・・数と数との操作(暗算、筆算)
④文章題・・・さまざまな数の変化や操作を推論する
算数障害スクリーニング検査(就学前検査)で測る能力
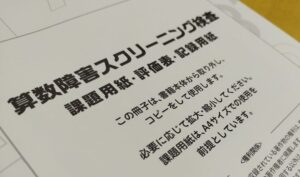
本書では、検査時の年齢により2種類の検査が用意されています。
・就学前のお子さんの数に関する知識や技能を評価する「就学前検査」(幼児・小学1年生対象)
・算数教科で習得される内容のうち、算数障害に関する内容を評価する「就学後検査」(小学1年生3学期以降対象)
本検査を実施することにより、算数に関する認知のアンバランスの傾向を捉えることができます。
①数処理
「数処理」とは、数の3つの側面、数詞・数字・具体物を対応させること。
「数処理」は計算の前段階であり、算数・数学では、まず数詞・数字・具体物の対応関係が習得されます。
・数詞「いち、に、さん・・・」→音としての数(聴覚的・言語的シンボル)
・数字「1、2、3・・・」→文字としての数(視覚的・言語的シンボル)
・具体物「●●●・・・」→数えられるものとしての数(視覚的で操作可能なもの)
数詞「いち、に、さん・・・」は音としての数(聴覚的・言語的)、数字「1、2、3・・・」は文字としての数(視覚的・言語的)、具体物は数えられるものとしての数(視覚的で操作可能なもの)というように、それぞれ関連する能力に特徴があります。
そのため、それぞれの能力が十分に伴っていない場合、例えば「数字は書けるが読めない」などのようなことが起こってしまいます。
数処理では、以下の能力を測ります。
いくつまで数唱ができるか
数を正しく数えるには、数を正しい順序で唱えること(=正しい数唱)が必要。
聴覚的な記憶力や継次処理能力(一つ一つの情報を時間的な順序で処理していく能力)に困難がある場合、数詞の系列(数の順番)を正確に覚えられないため正しい数唱ができない、すなわち、正しく数えられなくなってしまいます。
本調査によると、以下のような推移で安定した順序で数唱ができるようになっていきます。
数詞の安定した順序の獲得
・3歳6ヶ月くらいまでに「1、2、3」
・4歳までには「1~10」
・5歳3ヶ月までには「1~15」
・5歳9ヶ月までには「1~20」
・6歳2ヶ月までには「1~30」
・6歳5ヶ月までには「1~50」
就学前に意識すること
まずは、お風呂に入っている時など生活の中で数を唱えることで、「数詞」が正しい順序で言えるようになることが重要。
「数詞」の習得で大切なのは、「10まで数えるのはすぐ終わるけど、100までだとたくさん時間がかかる」など、子どもの感情や感覚と対応づけて唱えることです。
具体物が正しく数えられるか(数詞とモノの一対一対応)
数詞が安定した順序で正しく言えるようになると、次に、それを使って具体物を数えること(計数:カウンティング)ができるようになります。
しかし、数を正しい順番で唱えられていても、1つのモノに1つの数詞を結びつけること(数詞とモノの一対一対応)ができていないと、正しく数を数えることができません。
目と手の協応(目で見た情報に合わせて体を動かす)や視覚的な短期記憶力(見たものをすぐに覚える力)が弱いと、モノを数えるとき、既に数えたものを覚えていられないために同じものを何度も数えてしまったり、逆に飛ばしてしまったりします。
本調査によると、12個のおはじきを横にまっすぐ並べたものをいくつまで数えられるかを見た場合、4歳までで5個、5歳までで10個、6歳で12個すべてを正しく数えることができるようになります。
また、たくさんのおはじきの中から指定された数を取り出す課題では、「4個ちょうだい」を正しくできるのが5歳、「7個ちょうだい」や「12個ちょうだい」を正しくできるのが5歳6ヶ月以降となります。
就学前に意識すること
「数詞」がある程度正確に言えるようになったら、「数詞」を使ってものを数える(計数)ことをやってみましょう。
正しい順序で言える「数詞」の範囲内で数えてみればよく、就学前なら1~20程度までで十分です。
数えるときに、すでに数えたものとまだ数えていないものを区別できる工夫(数えるものを一列に並べるなど)が自分でできるようになることも大切。
また、たくさんのものの中から目当てのものだけを限定して数えられるかどうかも重要です。
数字がどれくらいわかるか(数詞と数字の対応)
時計やテレビ番組など、生活の中で数字を見る機会があると、数詞を数字にマッチングすることができるようになりますが、2桁以上の大きな数については、十進法の数詞の言い方や数字の表し方の理解が必要になります。
十進法とは、10のまとまりごとに1つ上の位に上げていく数の表し方のこと。
また数字を書く位置によって数の大きさを表すきまりのことを「位取り」と言い、十進法と位取りの原理によって,0から9の10個の数字を使って数を表す方法を「十進位取り記数法」といいます。
この「十進位取り記数法」が理解できていないと「さんじゅういち」を「301」と書いてしまったり、桁の大きい数字を読めなかったりと、大きな数の処理につまずいてしまうことがあります。
本調査によると、おおよそ4歳~4歳2ヶ月で「2、3、5」、4歳3ヶ月~4歳5ヶ月で「4、7、9」、4歳6ヶ月~4歳8ヶ月で「6、8、10、12」、5歳~5歳2ヶ月で「11、14」、5歳6ヶ月~5歳8ヶ月で「20」という数字が読めるようになっています。
就学前に意識すること
数字は、時計など生活の中で見る経験ができるものですが、就学前の子どもにとってその形を覚えるのは大変なこと。
書ける必要はまだありませんので、手元にある数字のカードやシールなどから選ばせたり貼らせたりするなど、遊びながら数量(集合)と数字をマッチングできるようにしていきましょう。
➁数概念
数には序数性(順番をあらわす)と基数性(量を表す)という2つの側面があります。
基数性・・・その数が1に対してその量をあらわしていること
序数性を理解できているか
序数性とは、数が系列であって順序を表していること。
順序としての数(序数性)が理解できない子は、数の系列がなかなか習得できない、つまり「いち、に、さん、し、ご・・・」と数を順序よく唱えられません。
そのため、ざっくりとしたおおよその数の量感はわかりますが、正確な数の理解や数の操作ができません。
上で述べたとおり、4歳までには「1~10」までの数詞を安定した順序で言えるようになっていきますが、それだけでは、数概念としての序数性を理解できているとは言えず、「5は4よりもむこうにある」「6は7の手前にある」など数(数詞)の位置関係の順番(系列)が把握できたときに”序数性が獲得できた”と言えます。
基数性が理解できているか
基数性の理解とは、数の「量」としての側面が理解できていること。
数が「量」をあらわしていることが理解できないと、数の操作はできても、数が示す意味や、数を操作することの意味がわかりません。
それなのに、計算問題は計算の方法が分かって答えられることもあります。
このようなタイプの子の場合、計算問題はできても文章問題から立式することができず、小学校低学年のうちは問題が生じなくても、高学年になるに従い問題が出てくることがあります。
就学前に意識すること
聴覚的に習得した数詞を言いながら指をさして具体物を数えると、最後に言った数が具体物の数(集合数)になります。
このことを理解するには、「みかんは何個ある?」などと聞かれて「いち、に、さん。だから、さん個。」と答えることを経験することが大切。
はじめのうちは言い方のルールとして知り、その後、集合数をあらわしていることを理解していきます。
また、「クッキー2個と3個」「みかん4個と3個」など、いろんなもので数を比べて、どちらが自分にとってどういう意味があるのかを話してみましょう。
クッキー2個と3個を比べて「たくさん食べたいから3個のほうがいい」、「3人家族だから3個がいい」など、意味を考えることが大切です。
文章題(数をイメージして操作できるか)
「あなたはりんごを4個持っています。私があなたにりんごを2個あげると、あなたのりんごは何個になりますか」などの文章題を耳で聞きいて答えを出します。
文章を理解し、具体物を操作せずにイメージで数が操作できるかを検査します。
まとめ
算数障害スクリーニング検査(就学前検査)で測る能力からみる
就学前に身につけておきたい算数の力
①数処理
数の3つの側面、数詞・数字・具体物を対応させる
・ 正しく数唱ができる
・正しく計数(カウンティング)ができる ※数詞とモノの一対一対応
・数字がわかる(数詞と数字の対応)
➁数概念
・序数性(順番をあらわす)の理解
・基数性(量をあらわす)の理解
・文章題(数をイメージして操作する)