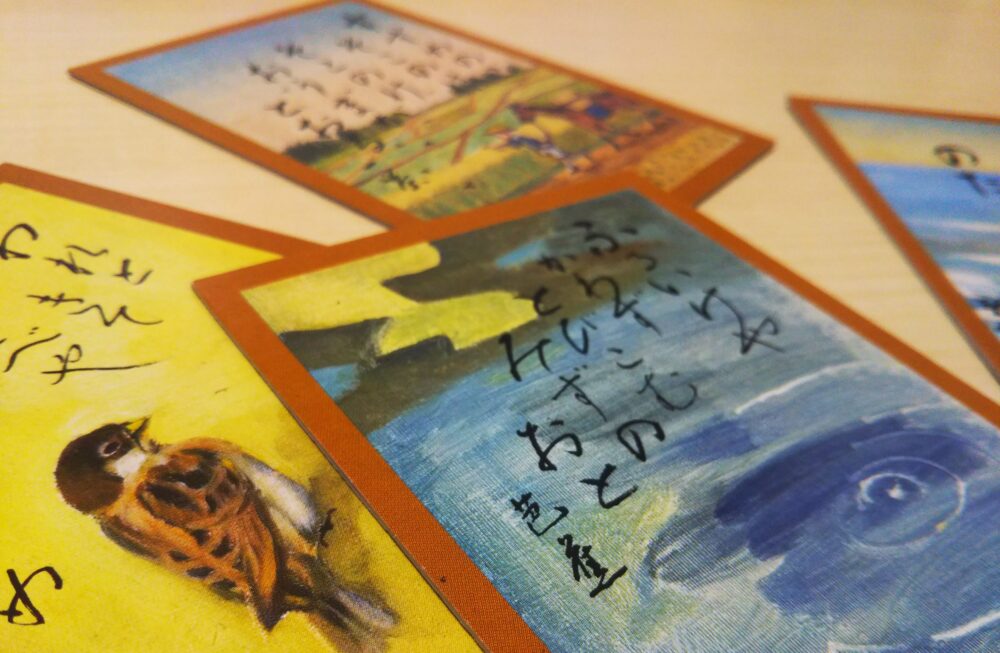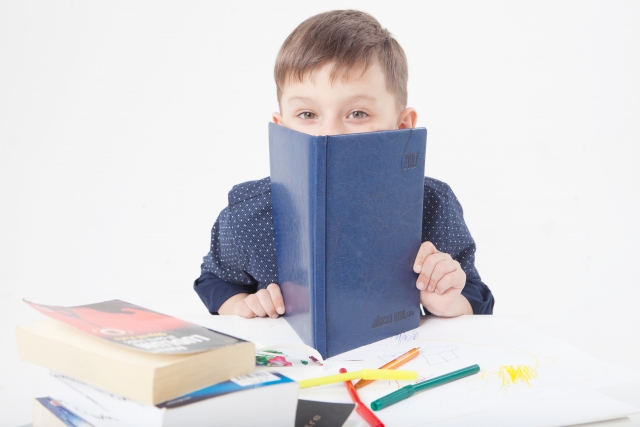暗唱とは、文章を記憶して何も見ないでそらんじること。
暗唱に取り組んでいくうちに、最初はなかなか憶えられなかった子も、だんだん、おぼえられるようになるまでの時間が短くなってきます。
つまり「記憶力」も、計算力など同じようにトレーニングで鍛えることができるのです。
私の教室では、2歳児さん~小学生まで全ての学年で「暗唱」に取り組んでいます。
今回は、おうちで「暗唱」に取り組んでみたいという方のために
- 効果が出る「暗唱」の取り組み方のコツ
- 教室で使用している「暗唱」の教材
- 「暗唱」に関するよくあるご質問と解答
について、お伝えします。
スポンサーリンク
「暗唱」トレーニングで効果を出す3つのコツ
①あせらず、ひたすらインプットする
暗唱トレーニングの最初の段階では、暗唱の課題をおうちの方が読んであげたり、CD教材をかけ流したりして繰り返し聞かせます。
この段階ではひたすら聞かせるだけで、お子さんに無理に言わせようとしないこと。
何度も聞かせてあげているうちに自然に覚えてしまい、そのうち勝手に口に出してそらんじ始めます。
お子さんが自分で口に出して言わずに親御さんに読んでもらいたがっているうちはインプットのチャンスととらえ、面倒がらずに何度でも読んで聞かせてあげましょう。
インプットなくしてアウトプットなし!
②親自身が暗唱してみる
お子さんに暗唱をさせるばかりでなく、親御さんご自身が暗唱課題に取り組んでみましょう。
親御さんが課題を音読している姿を見せたり、お子さんに暗唱を聞いてもらったりしているうちに、「おもしろそう」と興味を持ってお子さん自ら取り組んでくれるようになります。
また親御さんが言っているのを聞いて自然に覚えてしまい、「あれ?次は何だっけ?」と忘れたふりをしてみると、お子さんが得意気に言ってくれることもあるでしょう。
ポイントは、あくまで親御さん自身が「好きでやっている」というスタンスで行うこと。親御さんが楽しんで取り組んでいる姿を見せることです。
音読・暗唱は脳の活性化にも!脳トレの一環として取り組んでみるのもいいですね。
③間違えても恥ずかしくない!と思わせる
お子さんによっては、「途中で言えなくなったり、間違えたらはずかしい」という思いから、暗唱することをためらってしまう場合も。
お子さんが途中でつまずいたり間違えた時に「違うよ、〇〇だよ」などと指摘したり訂正したりするのは逆効果。
がんばって口に出して言えたことを認めてほめてあげましょう。
また上記のコツ②のように、親御さん自身が暗唱に取り組み、間違えたり忘れてしまう姿を見せるのもよい方法です。
「暗唱」についてのよくあるご質問
私が教室の生徒さんの保護者からよくいただく「暗唱」の取組についてのご質問と、その回答をご紹介します。
「俳句や百人一首をおぼえて何か意味あるの?」
「暗唱」は、俳句や百人一首をおぼえることが目的ではありません。
暗唱課題に取り組むことで記憶の容量を大きく、また記憶するスピードをはやくしていく「記憶力」のトレーニングです。
ですので、暗唱の題材は、必ずしも俳句や百人一首でなくてもOK。
記憶力をやしなうこと以外にも、題材をとおして豊かな言葉や表現に触れるのも暗唱の目的のひとつです。
どうしても俳句や百人一首になじめないのなら、詩や絵本など、お子さんが楽しく取り組めそうなものを探してみてくださいね。
「暗唱の取組を、子どもがイヤがります。」
「子どもが暗唱を嫌がって、家でやろうとすると逃げてしまいます。」という場合、親御さんがお子さんに無理矢理言わせようとしていることが多いもの。
だいたいの子どもは「やらされ感」を嫌います。
親御さんが読んで聞かせたあと、おぼえたかどうかを試すために言わせたりすると、とたんにヤル気がなくなってしまいます。
お子さんが自分から言いたがらないのは、まだインプットの量が足りないということ。
その場合は無理に言わせようとするのではなく、ひたすら聞かせてあげることがポイントです。
暗唱の課題を目につくところに貼っておき、気がついた時に読んで聞かせてあげましょう。
そのようにして何度も聞いているうちに子どもは自然におぼえてしまいます。
そうなれば言いたくなるのが子どもの常で、自分からすすんで言い出すように!
また、お子さんが間違えたり言えなかったりした時に、「なんで覚えられないの?」などと怒ってしまっていませんか?
正解・不正解にこだわらず、お子さんが暗唱をしようとした気持ちを大切にして、大いにほめてあげるようにしましょう。
「句や文の意味を教えてあげた方がいいの?」
暗唱は、意味の理解を求めずそのままおぼえる右脳の記憶。
ですので「意味はわからなくとも聞いた音をそのまま記憶し、そのまま言う」でOKです。
暗唱はおぼえる内容に意味があるのではなく、続けることで記憶力を高めること、すなわち、おぼえることそのものに意味があるのです。
ただし、お子さんの年齢が大きくなって左脳が優位になってきたり、お子さんの個性によっては、意味を理解しているほうが覚えやすいという場合も。
お子さんのほうから「これってどういう意味?」と聞いてきたり、ただ読んで聞かせてあげるだけではなかなか覚えられないという場合は、意味を教えてあげたり、お子さんと一緒に意味を調べてみたりすることで覚えやすくなる場合もあります。
「以前おぼえた句をすっかり忘れてしまっているんですが・・・」
これもよくあるご質問で、「一度おぼえたものを、しばらくするとすっかり忘れてしまっているのですが・・・それでいいんでしょうか?」というもの。
しかしながら、そのような場合も決して記憶から消えてなくなってしまっている訳ではなく、少しヒントというか、きっかけを与えるとちゃんと出てくることが多いです。
また、一度記憶したことも、何もしなければ忘れてしまうのは人間の摂理。
テストのための暗記のように記憶を定着させるには反復が必要ですが、暗唱の取組は、課題の内容をおぼえることが目的ではないので、定着させる必要はないのです。
スポンサーリンク
暗唱の取組におすすめの教材3つ
くもん 俳句カード・百人一首カード
「暗唱」は記憶することそのものに意味があるため、課題とするものは何でも良いのですが、五音・七音からなる俳句や短歌は日本人の耳に親しみやすく、リズムにのせておぼえやすいので暗唱課題に適しています。
レッスンでは、2歳児さん~年長さんでくもんの俳句カード、年中さん・年長さんでくもんの百人一首カードを使用しています。
リンク
脳を鍛える大人の音読ドリル
小学生クラスで課題としているのは「脳を鍛える大人の音読ドリル」。
夏目漱石の「坊っちゃん」や「吾輩は猫である」、宮沢賢治の「風の又三郎」「注文の多い料理店」、新見南吉の「ごん狐」など、誰もが子どもの頃にいちどは読んだことのある作品を含む日本名作文学が60作品掲載されています。
※関連記事:小学生の「音読」、効果と目的は?レッスンで使用しているおすすめ教材もご紹介します。
小学生の国語の宿題の定番、「音読」。近年、「音読」は小学校で重要視されています。こちらの記事では、私がレッスンで使用して…
七田 暗唱文集
私が以前、講師をしていた七田の暗唱教材。
百人一首・漢詩・漢文・近代文学・古典文学などが題材となっています。
冊子にCDが付属しているので、親御さんが読んであげなくてもかけ流しでインプットできるので楽ですね。
しかもCDの再生スピードが通常スピード→2倍速→4倍速→3倍速となっていて、速いスピードで聞かせることにより右脳に働きかけてくれます。
最後に
「暗唱」は記憶力をそだてることはもちろんですが、俳句や百人一首、日本文学などを題材にすることで、日本語独特の美しい響きや表現に触れることができるすばらしい取組。
ぜひ、おうちでの知育の取組のひとつに加えてみてくださいね!
※おうちでの右脳トレーニングの取り組み方を以下の記事にまとめています。ぜひ参考にしてみてくださいね!>>>七田(しちだ)のレッスンを再現しよう!おうちで右脳を鍛える取組まとめ
小学生の国語の宿題の定番、「音読」。近年、「音読」は小学校で重要視されています。こちらの記事では、私がレッスンで使用して…