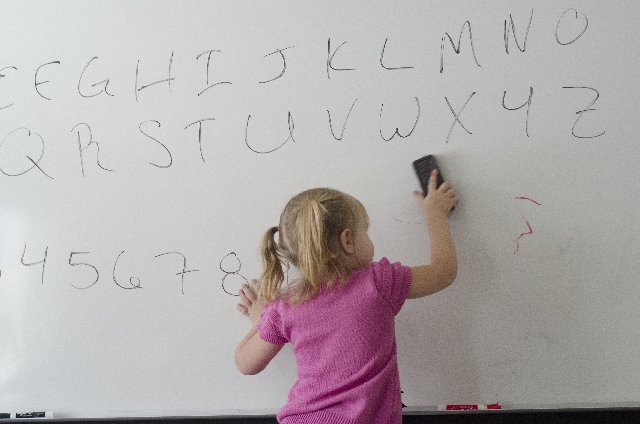数の概念の基礎から、小学校で習うかけ算・わり算の考え方まで・・・
おはじきは、「かず」を学ぶのに必要不可欠なものです。
今回は、”おはじき”を使って学ぶ「かず」の概念、”基礎の基礎”をご紹介します。
スポンサーリンク
「おはじき」で学ぶ数概念の基礎6種
①正しく数える~計数

あらかじめ取り出しておいたいくつかのおはじきを、「いくつあるかな?」と数えさせます。
正しい”計数”(数を数える)とは、数える対象のモノ1つに対し、数詞(いち、に、さん・・・)1つを当てはめること。
すなわち、モノと数詞を「1対1対応」させることです。
まずは数唱(数を唱えること)が正しくできることが前提となりますが・・・
数唱ができていたとしても、ちゃんとおはじき1つに1つの数詞をあてはめて数えられているかどうかがポイントです。
②”全部でいくつ”がわかる~基数性の理解

”基数性の理解”とは、例えばおはじき5個を「1、2、3、4、5」と正しく数えて、最後に言った数が、そのおはじき全体の量をあらわしていることがわかる、ということです。
上記①の「計数」で、取り出しておいたおはじきを正しく数えられたら、「ぜんぶでいくつだった?」と聞いてみましょう。
③たくさんの中から、指定された数を取り出す

たくさんのおはじきの中から指定された数のおはじきを取り出すことは、あらかじめ取り出しておいたおはじきの数を数えるよりもむずかしくなります。
「おはじきをたくさんの中から取り出す」という作業をともなうと、「〇個を取り出す」という本来の目的を忘れてしまいがちなのです。
おはじき以外では、‘’サイコロの出た目と同じだけチップを取り出す‘’など、ゲームをとおして「ぜんぶでいくつ」を意識する機会をつくるのもよいですね。
レッスンでは「クイップス」というゲームをとおして、‘’指定された数をたくさんの中から取り出す‘’ことを取り入れています。
ラべンスバーガー社のボードゲーム『クイップス』は、これから”かず”の概念をどんどん理解していきたい2歳児さんにおススメのボードゲーム。 付属のサイコロを用いて1から3までの数をあつかうゲームですが、手持ちのサイコロを使うことで、あつか[…]
④どちらが多いかな?~数の多少の比較

「赤のおはじきと青のおはじき、どちらが多いかな?」などと、数を比較させます。
”どちらが多いか”(数の多少の比較)を考える時の基本は「1対1対応」です。
赤のおはじきと青のおはじきをきちんと並べて(1つのものに1つを対応させる「1対1対応」)余っているほうが多く、足りない方が少なくなります。
子どもは見た目の量で惑わされがちなので、おはじきを間隔を広くとって並べて列が長いものと、間隔を狭くして列が短いものとでは、同じ数でも列が長いほうが”多い”と思ってしまったりします。
関連記事:同じ数を見つけよう/どちらが多いかな?~「数の多少の比較」
⑤あといくつで5?~数の構成

たし算や引き算の基礎となる『数の構成』は、ある数がいくつといくつでできているか(いくつといくつに分けられるか)ということです。
数の構成については、まずはおはじきを分けて「1と4で5」「2と3で5」「3と2で5」「4と1で5」「5と0で5」・・・などと見せていくインプットをしていきましょう。
その上で、「3といくつで5?」などと「あといくつでその数になるか(補数)」を考えさせるアウトプットで理解と定着をうながしていきます。
アウトプットにもおはじきが使えます。
おはじきを並べて、いくつあるかを確かめさせてから、両手でおはじきをシャカシャカして両方の手に何個かずつ隠します。
片方の手を開いて中のおはじきを見せ、反対側の手に何個あるか(=あといくつで全部の数になるか?)を考えさせましょう。
関連記事:
⑥いくつ多いかな?~「差」の理解

「赤のおはじきと青のおはじき、どちらがいくつ多いかな?」などと、数の差(ちがい)について考えさせます。
赤のおはじきと青のおはじきをきちんと並べた時(1つのものに1つを対応させる「1対1対応」)、余る数もしくは足りない数が、赤のおはじきと青のおはじきの数の「差(ちがい)」です。
「ちがいはいくつ?」や「いくつ多い?」という表現でわからないようであれば、「赤のほうがいくつ余るかな?」「青のほうがいくつ足りないかな?」など、「余る・足りない」という子どもに親しみのある表現で聞いてみましょう。
関連記事:
最後に
上でご紹介した以外にも、さまざまな数の概念を学ぶ場面で「おはじき」は大活躍してくれます。
以下の記事も、ぜひ参考にしてみてくださいね。
幼児期におはじきで学ぶ算数の基礎①~かずの基本からかけ算まで
就学前のお子さんに、毎日勉強する「習慣」をつけさせるのはなかなか大変なもの。 とはいえ、今までまったく勉強したことがない…
スポンサーリンク